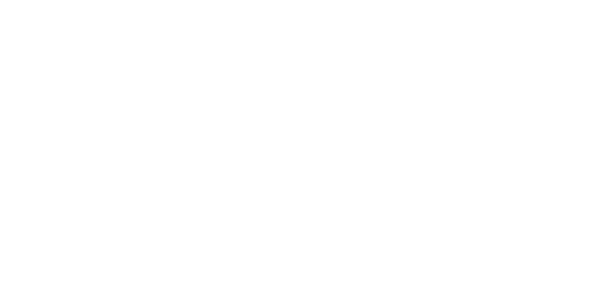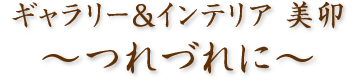糸
[ 2018-04-30 15:27 ]
日本中GW真っ只中ですね、お出掛け日和でもあり皆様如何お過ごしでしょうか?美卯オーナーです。去年の秋より度々ブログやFBページにてご紹介させて頂いてますが、手機織りを習い始めました。

きっかけの一つは松本民芸館にて当館を開かれた丸山太郎氏が作られた卵の殻を材料とする螺鈿細工を見たことです。
丸山氏は松本市にあるちきりや工芸店のオーナーとしても知られていますが、民藝品を収集したり、商うだけでなく、よりその神髄に近づくためには自らも手しごとに親しむ道を選ばれたことを知り、私も何かモノづくりをしてみたくなりました。
一方、私の地元一宮市は昔から紡績で知られた街であり、その方面に関る友人知人たちの話から織物に興味をひかれていて、いつかは自分も布を織ってみたいと・・・。
そしたら「念ずれば通ず」でしょうか?知人宅にある元織物工場であったのこぎり屋根工場跡に手織機を持ち込んで手織物教室を始めることになり、すぐに参加させてもらいました。
まだ初歩も初歩で思いもよらない糸の性質に翻弄されながら自らの手でモノを生み出す醍醐味の一端を愉しんでいます。
50の手習いですが、頑張ります!(^^ゞ
伝統技術を引き継ぐために
[ 2018-02-24 17:24 ]
尾張地方は寒さの底を漸く抜け出したようで日中はとても過ごしやすくなってきました、美卯オーナーです。
最近時々耳にする話題として「2025年危機」というのがあります。
経済産業省によると団塊世代の大量引退時期が迫り日本の中小企業の3社に1社、127万社が2025年頃にはに廃業の可能性があるというもの。
雇用650万人、GDP22兆円が消失する可能性があるといいます。しかもそのうちの約半数が黒字企業とも、、、。
工芸の世界でも久しく後継者不足の問題が語られ、既にいくつかの伝統技術が失われていきました。
今回の経産省の問題提起でも特に歴史ある老舗企業、日本の工芸品を作り続けてきた伝統企業が多く含まれています。
技術者(職人)、中小企業どちらも血縁による継承が難しい時代。
ならばどうするか?ということで、企業ならM&A(合併・買収)など考えられ、またそこまで大がかりでなくとも第三者が継承出来るような仕組みづくりなど、国も今までは“創業”を後押しする政策でしたが、これからは今ある優良な事業所の事業継承に注力する方向になるとかー。
ですが、伝統工芸の世界を永年みてこられた方々ほどそれはなかなか容易でない事と思われるでしょう。
伝統、技術を伝えるには時間と手間がかかります我が子でも難しいのに他人では尚更、、、。
でも、若者のなかにはチャンスがあればそういった伝統工芸の世界に飛び込んでいきたいという方たちも少なからず存在するのも事実。
ならばそういった「第三者」が修行して、学ぶための経済的な後押しになる制度など、技術も継承できる仕組みづくりを今からでも整備して、モノづくりの先輩方が後継者を諦めないで未来に希望を繋げられるようになればと願います。
七草粥
[ 2018-01-07 14:48 ]
新年を迎えて早7日、お正月の行事も一段落といったところですね。美卯オーナーです。

今日は正月7日なので、七草粥を焚きました。
ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、せり、なずな―♪
この日七草粥を食べるのは、正月のご馳走でオーバーワークな労わるためと言われています。
そのいわれの通りか、厳寒のせいか胃腸が弱り気味なのでとても美味しく頂きました。
この習わしもまた毎年の楽しみなのですが、今年も無事迎えられて心より感謝です。
そして、こうしたちょっとした汁物のお料理に便利で、中身をより素敵にみせてくれるのが、この小鹿焼の器です。
“コロンッ!”としていて掌にスッポリ収まってかわいらしいのも大好きな理由。感触がとてもイイんです♡
今年もお気に入りの器で毎日を楽しみたいと思います☺
2017年はシンギュラーポイント?
[ 2017-12-02 18:22 ]
とうとう12月、今年もアッという間に過ぎ去っていきそうです、美卯オーナーです。とはいえ、今年もいろいろありました。まだゆとりのあるうちに少しとりまとめていきたいかな~と。
2017年は公私にわたりターニングポイントになる事象が多岐の方面であったように思います。
こういう時期の事をシンギュラーポイント(=分岐点、特異点)と呼び、後年あれが節目だったといわれることがあります。
もう後戻りのできない、新しい次元へ移行して社会が急激に変化するため、大きな価値観の転換(パラダイムシフト)がおきるとも、、、。
それは人の世に限った事ではなく、自然界でも極端な気候変動が連続して誰の目にも明らかな変化が起きています。
人間も自然の一部と考えれば人間の社会と自然界の動きが連動するのは当たり前の事かもしれません。

、、、と前置きがながくなりました(^_^;)
私がこの一年感じてきたことは私たちの身近にある全てのモノは自然からのギフトであるということー。
食べ物、着るもの、住むもの全部自然に存在するものを材料に作られています。
ところがそのあって当たり前のように考えられてきたその材料が急速に自然界から消えていっていることをご存知でしょうか?
人間が生きていくための資源は様々にありますが、工業製品の主原料は石油を化学的にいくつもの工程を経て高度に加工された人造品であり、
それに対して民藝品のような手仕事でつくられる品のほとんどは自然界が産んだ状態に近く、その性質を活かした姿をしています。
だからこそ手仕事の世界では自然環境の変化は工業製品より早く直接的に、また目に見える形で影響を受けます。
民芸品の材料である天然素材は自然を相手にする仕事の不安定さから担い手が減少しているという面もありますが、生態系の変化から生産量が激減している材料があり、当店が関係している部分でいえば、ラッシチェアに使用する水草の生産が困難になっています。
加えて近年は日本中、いえ世界中でいつ、どこで気候の激変による災害に見舞われるかわかりません。
残念ながら今年7月には九州北部豪雨によって佐賀県日田市・小鹿田の里が被災。
採土場の崩落、土石流による唐臼(川の流れを使い臼で土を突いて細かくして陶土の原料にする装置)の流出破損といった被害がありました。そんな中現在は復興の工事の傍ら、生産を再開。小鹿田焼に関わる皆様のご尽力には頭が下がるばかりです。
小鹿田焼の里は永きにわたって自然と人間が共生しながら世代を重ね、焼物を生産してきました。
そして今、復興工事にあたっては次の災害に備えることを考えながら進んでいるといいます。
持続可能なモノづくりを目指して自然とどう折り合っていくのか、手仕事においても地球環境という視点は欠くべからざる課題であることを知らしめられた今年一年だったように思います。
(写真は2016年秋小鹿田 唐臼を撮影)
日本民藝館 西館にて
[ 2017-10-26 14:39 ]
久しぶりのスカッ!!とした青空のもと心地よい風が吹いている尾張一宮より、美卯オーナーです。
前回お話しましたように、今月は東京駒場にある日本民藝館へ。
民藝館へは何度かお邪魔させて頂いているのですが、今回初めて本館のお向かいに立つ西館を拝観できました。
日本民藝館西館は民藝の創始者である柳宗悦氏の自宅であり、氏が72歳で亡くなるまで暮らした邸宅です。
この西館は栃木県から移築された1880年建造の石屋根の長屋門と、柳氏自身が設計されたという母屋からなっていて、
長屋門をくぐり、広々とした玄関を抜けて1935年に完成したという木造の旧宅にはいると、当時の暮らしぶりを感じることができます。
ここは大都会・渋谷から井の頭線で僅か10分ほどのエリアでありながら緑の多い静かな文教地区であり、それぞれのお部屋とそこからの風景は古き良き時代の日本らしい佇まいを彷彿とさせてくれます。
邸宅の中でやはり一番心惹かれたのは柳宗悦氏の書斎。
部屋の壁面を覆い尽くす書籍の数々に圧倒され、加えて氏が数々の書籍、論文を著した机、その合間に寛いだ椅子がそのままに展示。
ここに座りながら読書をされているスタッフの方にはちょっとジェラシーです☺
また、3人のご子息の中でも長男宗理氏だけ特別な個室が与えられていたのは時代でしょうか?(2男3男は同室とか)(^_^;)
民藝の手仕事そのものの空間はとても心地よい空気が流れていました。
西館は常設公開ではなく、開館は展覧会開催中の第二水曜日・土曜日と第三水曜日・土曜日の月4日間です。
スケジュールを合わせて頂いてお出掛け下さいね☺
ウィンザーチェア ー日本人が愛した英国の椅子ー
[ 2017-10-20 16:18 ]
例年にも増してジェットコースターな気候変動に(@_@)ですね、美卯オーナーです。私は先週のお休みにまだ半袖でOKだった東京は駒場にある日本民芸館へ出掛けてきました。
(東京はそのわずか2日後には晩秋冷え込みに、、、(^_^;)
お目当ては~11月23日(木・祝)まで開催中の『ウィンザーチェア ―日本人が愛した英国の椅子―』

松本民芸家具の椅子でもあるウィンザーチェアの変遷をイギリスで作られた17世紀以降の椅子から辿るとても圧巻で見応えのある展示です。
今ほど技術も道具もない中で作り手が試行錯誤を繰り返した跡が今なお時代を超えてリアルに伝わってくる椅子ばかり。
作り手の息遣いが伝わってくるようで、見飽きません。
時にはしゃがんで座板の裏側を除く私の姿にスタッフの方々は呆れていたかも、、、(^_^;)
そして、素材である木にも注目。
今回は使われている木材の種類までは記載がありませんでしたが、英国では当時どの様な木を使って家具をつくっていたか興味深いところです。
曲げ木や挽き物のスピンドルも面白いのですが、私は座板の形状に興味が惹かれます。
座る側の面はある程度キレイにつくられていても裏側は自然の姿のまま塗装されていたりして、その武骨さが良い味わいになっていたり―。
今回展示された椅子の中には松本民芸家具所有・松本民芸生活館に所蔵されている椅子もいくつか展示されています。
松本生活館には何度かお邪魔したことがあるので、久々の再会になった椅子も―。
家具の中でも椅子は人の身体に最も密接に関係し、現代生活ではなくてはならない道具となりました。
それも先人たちの快適な道具としての椅子への希求と努力あっての賜物であることを識るよい学びの機会となりました。
ウィンザーチェアのその在り様は民藝の世界や木の文化など多様な視点から多角的に面白く眺めることができます。
この秋一押しの展示です。是非お出掛け下さい。
#ウィンザーチェア #松本民芸家具 #ウィンザーチェア―日本人が愛した英国の椅子― #民藝好きとつながりたい
ギャッベ織り糸の不思議
[ 2017-10-09 13:30 ]
三連休最終日、秋というには暑いくらいですねいかがお過ごしですか?美卯オーナーです。

・・・とはいっても秋は駆け足でやって来ます。
今のうちに暖かいインテリアの模様替はいかがでしょうか?
写真はイランの遊牧民カシュガイ族のお姉さまたちが農作業や家事の合間に心を込めて織ったパステルカラーのギャッベです。
デザインもカワイイのですがこの一枚の何よりの特徴は使われている糸の“染”。
ギャッベの糸は遊牧民の育てた羊毛を主に植物系の天然染料で染めますが、この糸は更に遊牧民の日常になくてはならない食品を染料に混ぜて染め上げています。
その食品は何ってわかりますか?ヒントは遊牧民の食卓です☺
遊牧民はヒツジを飼い、そのヒツジの食べる草を求めて遊牧地を転々とテント生活をしながら代々暮らしてきました。
草原にある遊牧地は街から離れているから食料をはじめ衣食住は自給自足することになります。
その生活の中から生まれ、住居の道具として発達してきたのがギャッベ絨毯ですが、そういった背景から使われる材料も身近なものに限られます。
さて、わかりましたか?
答えは、「ヨーグルト!」です☺
遊牧民は家畜の乳を使ってバターやチーズ、そしてヨーグルトを家庭で作って食べてきました。
そのヨーグルトを染料に混ぜて羊糸を染めることでパステルカラーに糸を染めることができるようになったのです。
私には詳しい経緯は不明ですが、遊牧民の誰かがある日食事をしながら閃いたのでしょうか?想像が膨らみます☺
原色のギャッベも美しいのですが、パステルの優しい色合いのギャッベは心も体もほっこりさせてくれるのです☺
#パステルカラーのギャッベ絨毯 #かわいいギャッベ絨毯 #一年中ギャッベ絨毯 #ギャッベ絨毯一宮市
金城窯三代の系譜
[ 2017-10-07 11:57 ]
今日は冷たい秋の雨が降ります、夏から秋へ皆様衣替えは間に合いましたか?美卯オーナーです。美卯では「金城窯三代と沖縄の器」の特集を開催中―。
「金城窯三代」とは沖縄初の人間国宝に選ばれた陶工・金城次郎氏から長男の敏男氏とその子息たちに渡る器の系譜であり、代を重ねることによる器の変遷を見て頂けます。
是非ご覧になってみて下さいね。

写真(上)は敏男氏による線彫りの魚
写真(下)は敏男氏長男・吉彦氏の線彫り魚
高山・日下部民藝館1
[ 2017-10-02 16:18 ]
10月になりました。一雨ごとに秋が深まっていきますね、美卯オーナーです。
今夏の日本民藝夏期学校・高山会場のメイン会場の一つとなった日下部民藝館をご紹介します。
高山市中心・下二之町にある明治12年(1879年)完成の町屋です。
高山は幕府直轄の天領となったことから商業が盛んになり町人の街として発達しました。
日下部民藝館は日下部家の邸宅であり、江戸時代は高山代官所の御用商人を務め、両替屋とか金融を生業とした家系です。
高山は木造建築の宿命でしょうか?度々大火に襲われており、現在の邸宅も明治8年に旧宅が消失した後、場所を移して現在の地に建てられました。(9代目当主の時代)
現ご当主であり、日下部民藝館館長の日下部勝氏の説明によると、名工と呼ばれた棟梁・川尻治佑により江戸時代の建築様式そのままのにこのお屋敷は建てられたそうですが、川尻棟梁の建築はとても男性的で豪壮なディテールであり、明取りの窓や梁と束柱の木組みなどにその特徴を見ることができます。

比較として日下部邸のすぐ隣にある吉島家住宅を見ると面白いそうです。
吉島家住宅は日下部邸と同じ大火で焼けた後現在地に移転再建されましたが、明治38年再び火災で焼け、明治40年名工・西田伊三郎棟梁にて建てられました。生業は造り酒屋だったので軒先に杉玉が飾られている写真をご覧になった方は多いと思います。
内装はとても繊細な空間であり、日下部邸を剛とするなら柔と言えるでしょう。
実際に住むことを考えなければ大胆な日下部邸のディテールが私は好きですが・・・。
高山を訪れたら、是非この2邸をご覧になって下さい。飛騨の匠の魂を感じる空間です☺
新着記事
- 2023.09.02 つれづれじゃないけれど☺️
- 2023.01.20 寒中お見舞い申し上げます
- 2022.12.08 美卯・開業17周年ありがとうございます
- 2022.09.10 あなたの作品(アート・クラフト)発表してみませんか?
- 2022.05.23 松本民芸家具・価格改定のお知らせ
カテゴリ
アーカイブ
- 2023年9月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (3)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (5)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (3)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (7)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (9)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (7)
- 2017年6月 (3)